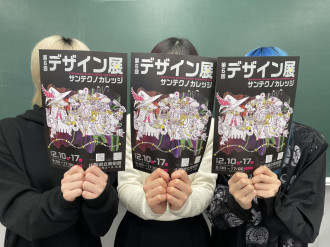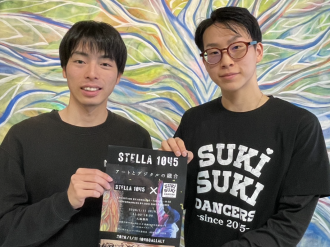山梨英和大学(甲府市横根町)の「サービスラーニング」の授業で制作した「音声付き甲州弁かるた」の完成披露・贈呈式が6月12日、同大図書館で行われた。
サービスラーニング科目は、教室での学びを活用しながら、コミュニティーでの活動を通して地域社会の実態やその問題を客観的に理解し、問題発見・解決力やコミュニケーション力などを高めていくことを目的として、2年生~4年生の選択授業として開講している。
2023年度は昨年9月に授業が始まり60人ほどの学生が参加。グループに分かれて16のプロジェクトが立ち上がった。同プロジェクトは、山梨県出身で同大3年の黒崎未来さん、深澤晴彩さん、三浦愛以さん、仙洞田朱音さん、弓田美恵さんの5人が集まり、チーム「ててて!かるた」を結成。近年、若い人たちが甲州弁を使う機会が減少していることから、方言を保存し、継承することが重要であると考えプロジェクトを始めたという。全15回の授業の中で、アイデア出しや校正・例文の作成、録音などを行った。
甲州弁の音声を録音するため、2001(平成13)年に地域の主婦ら18人で結成された「山梨むかしがたりの会」にメンバーに連絡を取り、協力を得ることになったという。甲州弁の民話の復活や次代への継承を目指す同会。現在は、20~90代の会員36人が4グループに分かれて活動し、図書館や学校での公演のほか、毎月学習会や全体研修会を開き、資料から昔話を甲州弁で再構成する「再話」にも取り組んでいる。2017年度おもてなしのやまなし知事表彰されたほか、2022年度には代表の藤巻愛子さんが県出身者で初めて久留島武彦文化賞個人賞を受賞した。
かるたの札は「あ」から「わ」まで全て甲州弁で作成。例えば「あ」は「ありんどう(アリ)にくっつかれた」、「い」は「いいさよー、いいさよー」といった具合。各札にはQRコードが付いており、スマートフォンで読み取ると甲州弁の発音を聞くことができる。藤巻さんの校正を元に、イントネーションを追加した読み札の文章や標準語も併記し、意味が理解しやすいよう工夫した。完成品は「富士フイルムビジネスイノベーション」の協力で印刷された。
式では、メンバーからの最終報告発表の後、「山梨むかしがたりの会」と図書館にかるたを寄贈した。
三浦さんは「音声を付けるときに誰に頼むか見つけるのが大変だった。イラストを変えて作ってみたい」、仙洞田さんは「家族で甲州弁を使う人がいなかったため、なじみがなかった。個人的に甲州弁を知るきっかけにもなった。形になったのでうれしい。音声を付けるのが難しかった」、深澤さんは「山梨に住んでいても甲州弁を話せない友達が多かった。山梨の魅力を若い人が継承していくのが大事。音で聞く機会がなかなかないので、スマホやPCで聞けるようになればいいと思った。目に見える形で残せて良かった」、黒崎さんは「地域に関わることができる先生のゼミに入っているのでこの経験が生かせるのでは。卒業した後も後輩たちに引き継いでもらうなどして、後世に甲州弁を残していけたら」と、それぞれ話す。